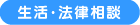 |
生活相談を随時、行っています。ご連絡ください
●法律相談
●5月10日(土)
午後5時〜7時
日本共産党本町事務所へ
お越しください
●5月15日(木)
午後2時〜3時半
区役所5階 日本共産党控室へ
お越しください
●朝の駅前宣伝
武蔵小山駅 火曜日 午前7時45分ごろから
西小山駅 水曜日 午前7時45分ごろから
目黒駅 木曜日 午前7時30分ごろから (石川議員と隔週)
※天候や仕事の都合で変更の場合があります。
|
|
|
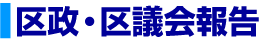
|
■「全てのこどもの育ちを応援」というが… こども誰でも通園制度は問題点だらけ
|
目黒区は、こども誰でも通園制度の導入を検討しています。この制度について、私は新年度予算質疑の中で取り上げました。
26年度の実施をめざす
この制度は、ゼロ歳6か月から3歳未満の子どもを対象に、親の就労要件を問わず、保育園などに月一定時間の利用枠のなかで、時間単位での利用を可能とする制度で、法律上の制度として位置づけられました。国は2026年度から新たな給付制度として全自治体での実施をめざしています。
これまで、いくつかの自治体で試行的事業として実施され、補助単価は1か月10時間以内で1時間単位で利用可能とされ、事業者の補助単価は子ども一人1時間当たり850円と保護者から徴収する利用料300円の1150円でした。
25年度は、こどもの年齢によって職員配置数に違いがあることなどを考慮し、1時間当たり、ゼロ歳児は1300円、1歳児は1100円、2歳児は900円に増額されます。利用に応じた出来高払い方式です。
国は「全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化する」ことを掲げていますが、この制度には大きな問題点がいくつもあります。
営利企業が参入
その一つは、保育事業の実績のない営利企業でも、施設の基準を満たせば実施可能とされている点です。昨年8月時点で試行的事業を行っている800事業所のうち株式会社立が85事業所あります。
出来高払いの単価と営利企業参入という仕組みは、利用者が休めば報酬が減り経営が不安定になることや、子どもの安全の確保や発達・成長を保障することができるのか不安の声も上がっています。
私は質疑の中で、この点について区としてどう認識し、対策を打とうとしているのか聞きましたが、区は「広く周知を行い、事業者の安定的な経営につなげていきたい」と述べるにとどまりました。
自治体の関与が薄まる
2点目は、区市町村の関与の問題です。
誰でも通園制度は、法律上は保育ではなく乳幼児または幼児への遊びおよび生活の場の提供とされています。児童福祉法で定める保育所制度には、区市町村に保育の実施義務がありますが、この制度は区市町村は利用対象者と事業者の認定を行うだけで、利用調整は行いません。利用者が自ら施設の空きを確認し直接的に申し込む直接契約方式となります。
保育をはじめとする他の子育て支援制度と比べても区市町村の関与が大きく後退していく恐れがあり、この点を区に問いました。
区は「人員配置、設備基準を確認して認可する。それに基づいて指導、監督することもできる」と一般論を述べただけでした。
こども無視の自由利用
3点目は、自由利用の問題です。
この制度は利用する施設・曜日を決めた定期利用のほか、これらを固定せず、居住地以外の施設でも、空きがあれば利用できる自由利用が認められています。
自由利用で、乳幼児の子どもの発達にとって重要な特定の大人との応答的なかかわりや、情緒的な絆をはぐくむことはできるのか、大いに疑問です。また、保育施設における死亡事故は預け始めが非常に多く、毎回違う施設に預けることが可能な自由利用は、重大事故のリスクに子どもたちをさらすことになりかねません。医療的ケア児や障がい児も受け入れるもとで、この点のリスクを問いました。
区は自由利用の下で、私が指摘した問題点を認識しつつも、「運用については検討していく」と述べるにとどまりました。
職員に大きな負担
4点目は人員体制、職員配置の問題です。
この制度は、一時預かり事業と同様に保育士の有資格者は半分でよいとされ、保育士以外の人材も活用するとされています。
現在はただでさえ、区立、私立双方の保育園で人材の確保が非常に困難だといわれているなか、通園児を預かるということになると、在園児の保育を保障できなくなってしまうといった危ぐも広がります。保育関係者の事務処理が煩雑になる問題もあります。保育関係者の疲弊感が広がるとともに、こどもの安全が確保できるのかどうか、私は区に質問しました。
区は「みなし保育士の確保にも努めていく」などと述べ、「保育現場の業務負担については、国のシステムを導入し効率化を図ることで職員の負担軽減につなげていけると認識している」と実態にそぐわない答弁を繰り返しました。
「こどもたちにとって甚だ疑問」
私の質疑に対し、最後に子育て支援部長も「こどもたちにとって、今回の制度がどういう意味があるのか甚だ疑問」と答弁せざるをえませんでした。
今やるべきは、このような通園制度ではなく、公的責任で質の高い保育を提供できる制度をつくることです。
|
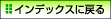 |
|