
|
■260号 障害者「自立支援」法案 応益負担の撤回を
|
関係団体との協議もなく
障害者に原則1割の定率負担を求める障害者「自立支援」法案の審議が5月11日から衆院厚生労働委員会で行われています。
サービス内容、利用者負担のあり方をはじめ、障害者施策での大きな制度変更にもかかわらず、法案作成が障害者や家族、関係団体との十分な協議もなくすすめられました。
定率負担は撤回を
山口富男衆院議員は、利用者負担の問題で、「障害者の所得保障や就労支援策が不十分な現状のもとで、こんな負担増には耐えられない」とのべ、定率負担撤回を求めました。
現在の支援費制度では、利用者の負担は所得に応じた金額になっています。ホームヘルプの場合、利用者の95%に負担を求めません。
通所者は負担19倍
ところが、1割負担になると、家事援助や身体介護などのホームヘルプでは現行月平均1000円が4000円へと4倍もの負担増になります。さらに、通所施設では、月1000円が1万9000円に19倍の負担増です。
財政優先で改悪
厚労省は、全体の負担増がわかっているだけでも年間700億円を上回る規模になることを認めました。山口議員は「これでは障害者の自立支援どころか自立を壊していくものだ」と批判。尾辻大臣は、現行の支援費制度が「財政的にいきづまり、持続可能性を追求しなければならなくなった」とのべ、財政優先で改悪したことを認めました。
生存権侵害だ
厚労省が定めた応益(定率)負担の「上限」でも、障害者の収入(障害基礎年金)の2〜3割の利用者負担になることを示しました。これは、「障害者の生存権侵害に踏み込むもの」です。
厚労省は、大幅な負担も「上限」があるので低所得者にきめ細かい配慮を行っているとしています。
しかし、障害2級相当の上限は月1万5000円で収入(障害基礎年金)の約2割、1級相当の人は月2万4600円で収入の約3割に及び、きめ細かい低所得者対策などありません。
50倍の負担増も
山口議員は、障害者の公費負担医療見直しがとてつもない負担増につながる事例として、心臓病患者の例をとりあげました。
30歳の1人暮らしで、心臓手術で20日間入院した場合、所得税が年額4800円以下だと食費の負担増も合わせて、現行の2300円から11万5490円へと50倍もの負担増になります。
「ここに障害者の人権を踏みにじる政策が出ている。変えるべきだ」。と、山口議員が追及したのにたいし、尾辻秀久厚労相は「それぞれのケースで精査しなければいけない。そのうえで答えたい」とのべ、精査が必要と認めました。
|
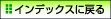 |
|